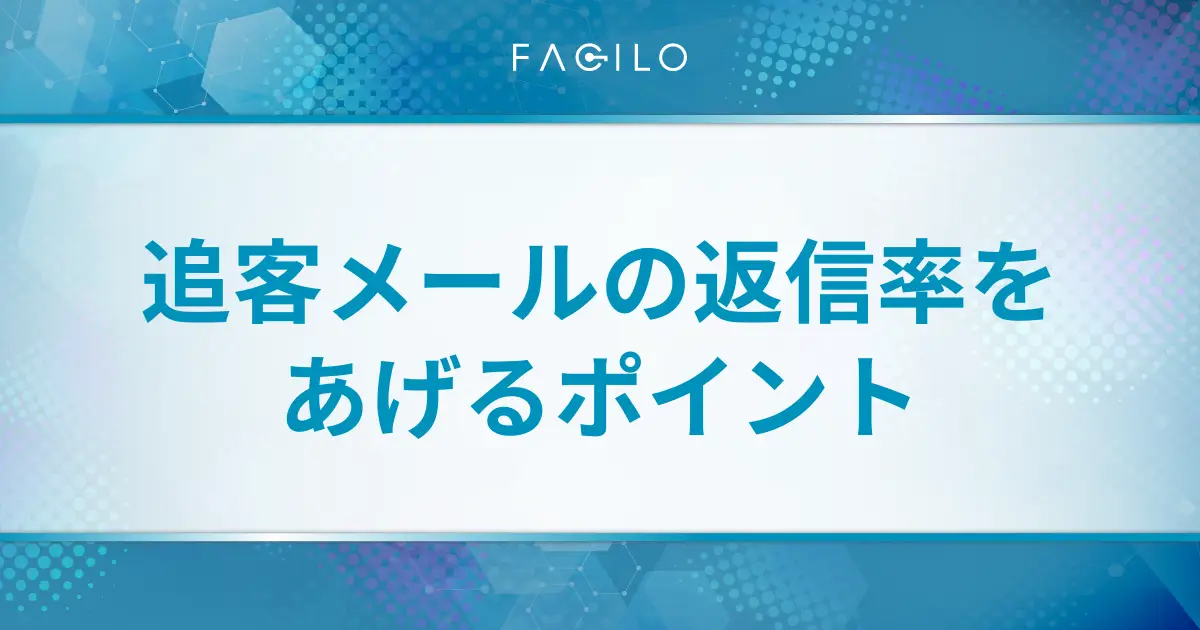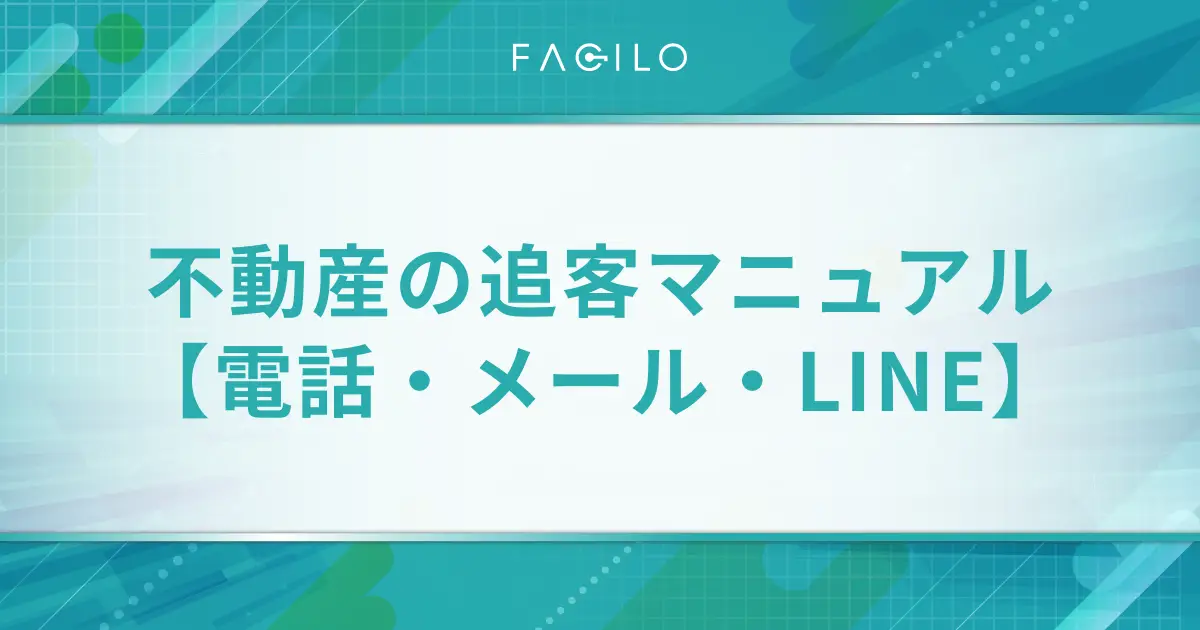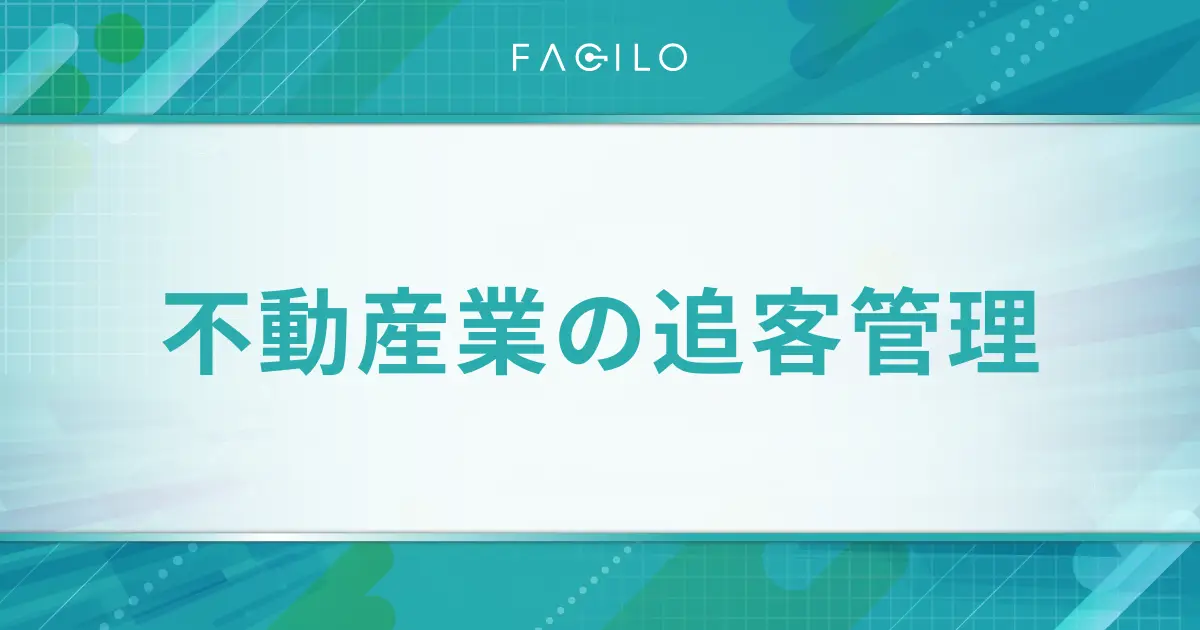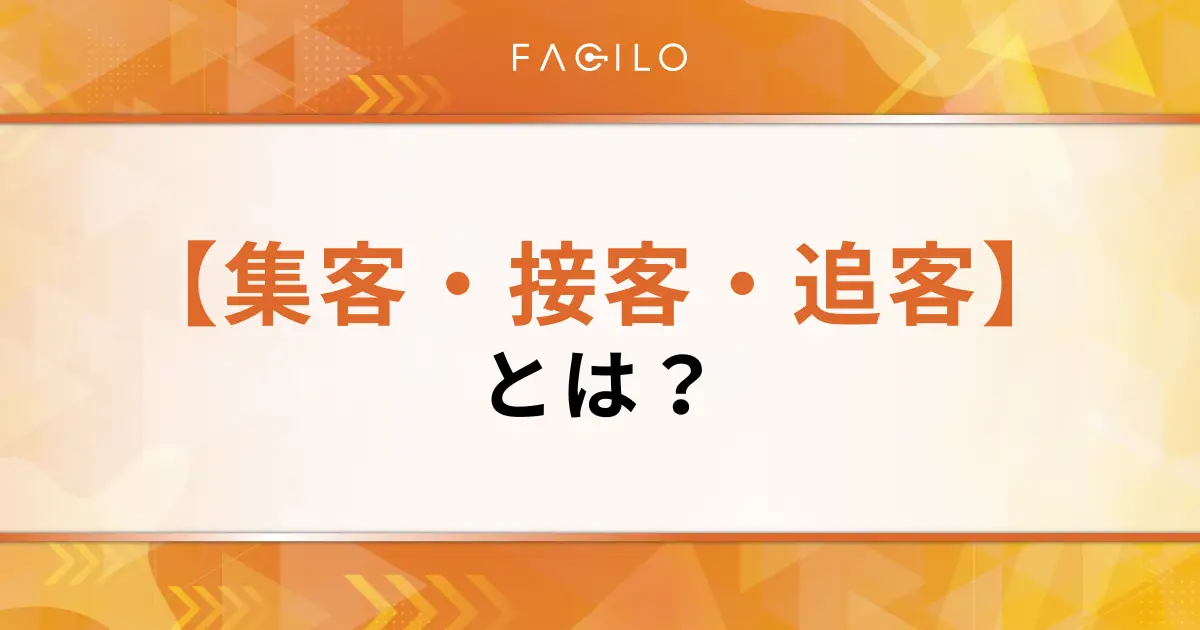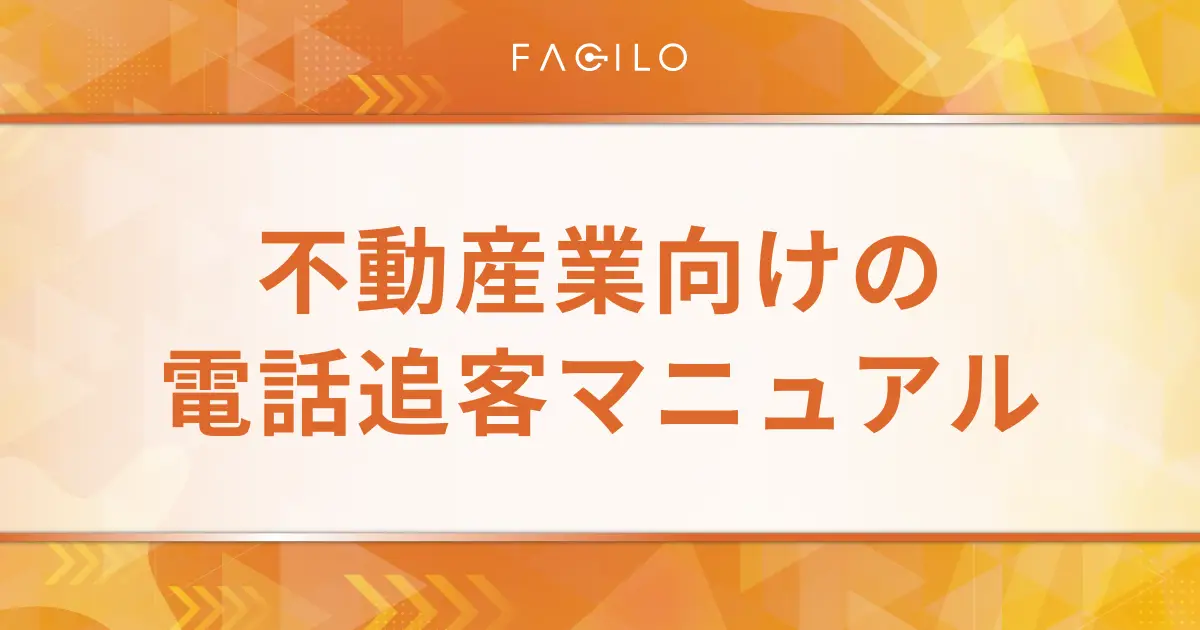
不動産仲介の報酬はどれくらい?仲介手数料の計算方法と金額一覧表も紹介
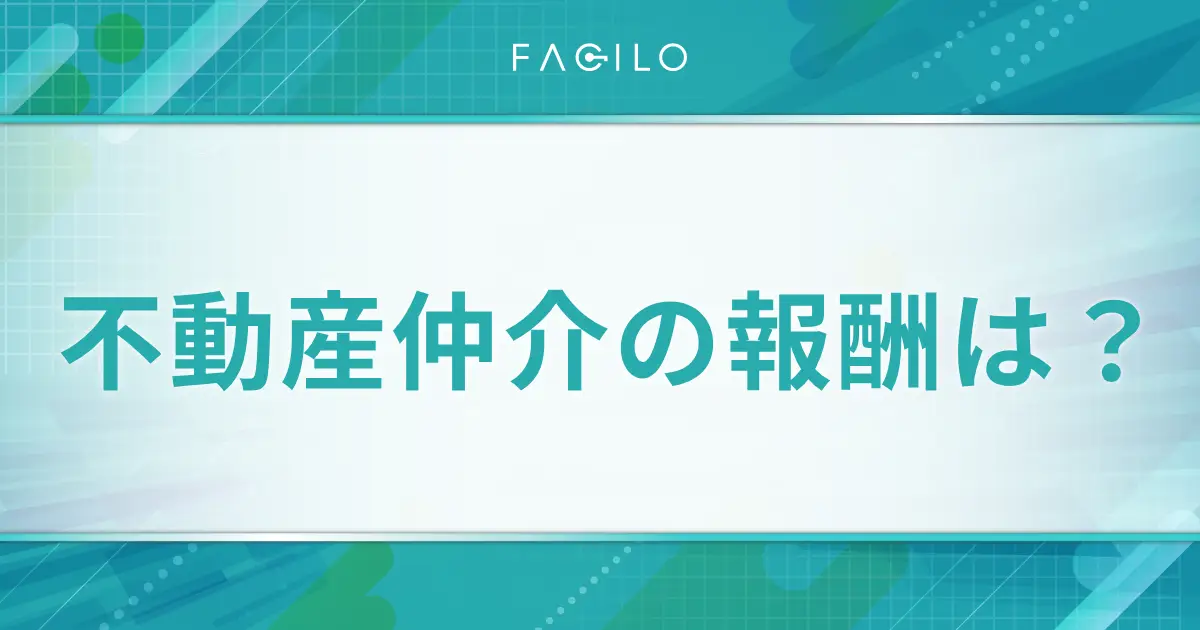
仲介手数料は、不動産会社が売買や賃貸の取引を仲介した際に受け取る報酬です。宅地建物取引業法によって上限が定められており、物件価格に応じて計算方法が異なります。
この記事では、不動産仲介の報酬である仲介手数料について、その仕組みや計算方法、法律で定められた上限額、支払いのタイミングまでをわかりやすく解説。
さらに、売買と賃貸での違い、手数料を抑えられるケースや例外的に高くなる場合についても詳しく紹介します。
不動産仲介の報酬とは?
不動産仲介の報酬とは、不動産会社が売買や賃貸の契約を成立させた際に、成功報酬として受け取る「仲介手数料」を指します。
この手数料は、物件の広告活動や内見調整、契約書の作成、重要事項の説明といった専門的な業務に対する対価として支払われるものです。
不動産会社にとって、この仲介手数料が主な収益源となります。ここでは、仲介手数料の基本的な仕組みについて解説しましょう。
売買と賃貸で異なる仲介手数料
仲介手数料は、売買契約と賃貸契約で計算方法や上限額が異なるものです。
売買契約の場合、物件の価格に応じて手数料の料率が決まっています。売買価格が400万円を超える物件では、次の速算式で簡単に上限額を算出可能です。
(売買価格×3%+6万円)+消費税
一方、居住用の賃貸契約の場合、不動産会社が受け取れる仲介手数料の組み合わせは、宅地建物取引業法および国土交通省告示(報酬告示)で定められた範囲内で、次のようになります。
- 貸主・借主の双方から:それぞれ「家賃の0.5か月分+消費税」ずつ受領(合計で家賃1か月分まで)
- 貸主のみから:貸主が「家賃の1か月分+消費税」を負担し、借主は無料
- 借主のみから:借主が事前に承諾した場合に限り、「家賃の1か月分+消費税」を負担し、貸主は無料
いずれの場合も、合計で「家賃1か月分+消費税」を超えて受け取ることはできません。契約書に記載された手数料が家賃の0.5か月分+消費税を超えている場合は、必ず担当者に確認しましょう。
参照:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
このように、売買と賃貸では手数料の仕組みが大きく異なるため、それぞれの計算方法を事前に理解しておくことが大切です。
仲介手数料を負担する人
仲介手数料を誰が支払うかは、契約の種類によって異なります。不動産の売買契約では、原則として売主と買主の双方が、それぞれ依頼した仲介会社へ手数料を支払います。
一方、賃貸借契約では、貸主と借主のどちらか一方、あるいは双方が合意の上で分担して支払うのが一般的です。負担割合は媒介契約書や募集条件に明記されているため、契約前に必ず確認しておきましょう。
費用負担の認識が食い違うと後のトラブルに発展しかねないため、事前の把握が重要です。
不動産仲介の報酬は仲介手数料から捻出されている
不動産仲介会社の主な収入源は、契約が成立した際に受け取る仲介手数料です。この手数料の中から、以下のような営業活動に必要な経費がまかなわれています。
- 広告掲載費
- 交通費
- 営業担当者の人件費
- 契約書類の作成費
- 事務所の維持費
そのため不動産会社は、限られた報酬の中で最大限の成果を上げるため、業務効率化やDX推進、サービス品質の向上に努めています。
顧客側もこの仕組みを理解しておくことで、「手数料が何に使われているのか」を把握でき、支払う金額に対して納得しやすくなるでしょう。
なお、仲介手数料は、契約が成立して初めて発生する成果報酬です。どれだけ時間や費用をかけても契約に至らなければ、報酬は一切発生しません。
不動産の仲介手数料の計算方法と上限
不動産の仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限額が定められています。これは、消費者が不当に高額な手数料を請求されないようにするためです。
ここでは、物件価格に応じた具体的な計算方法や、法律で定められた上限について詳しく解説します。
物件価格ごとの計算式と速算式
売買契約の仲介手数料の上限は、物件の売買価格に応じて3段階に分かれています。しかし毎回計算するのは手間がかかるため、実務では速算式が用いられるのが一般的です。
特に、売買価格が400万円を超える物件の場合、「(売買価格×3%+6万円)+消費税」という計算式で簡単に上限額を算出できます。
この速算式を覚えておけば、見積もりや契約時の精算を迅速に行えるでしょう。ただし、400万円以下の低価格帯の物件については、料率が異なります。個別の計算が必要になる点に注意が必要です。
200万円と400万円の区切りによる計算方法の違い
仲介手数料の料率は、取引される物件価格が200万円と400万円を境に変動する仕組みです。
具体的な料率は、200万円以下の部分は5.5%、200万円~400万円以下の部分は4.4%、400万円を超える部分は3.3%と定められています。
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限(税込) |
| 200万円以下の部分 | 売買価格(税抜)×5.5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 売買価格(税抜)×4.4% |
| 400万円超の部分 | 売買価格(税抜)×3.3% |
参照:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
この料率は国土交通省の告示に基づくもので、上限を超えた請求は宅地建物取引業法で禁止されています。違反した場合は指導や業務停止などの行政処分を受ける恐れがあり、不動産会社は法令を遵守した報酬の設定が必要です。
仲介手数料の金額シミュレーション
仲介手数料が具体的にいくらになるのか、「(売買価格×3%+6万円)+消費税」という計算式で価格帯ごとにシミュレーションしてみましょう。
以下に、不動産の売却価格に応じた仲介手数料の上限をまとめた早見表を紹介します。売却時の目安として参考にしてみてください。
| 売買価格(税抜) | 仲介手数料の上限額(税込) | 計算式(速算式) |
| 500万円 | 23万1,000円 | (500万円×3%+6万円)+消費税 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | (1,000万円×3%+6万円)+消費税 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 | (2,000万円×3%+6万円)+消費税 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | (3,000万円×3%+6万円)+消費税 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 | (5,000万円×3%+6万円)+消費税 |
例えば、2,000万円の物件なら72万6,000円が仲介手数料の上限となります。
(2,000万円×3%+6万円)×1.1(消費税)=72万6,000円
あらかじめ手数料の目安を把握しておくと、顧客に対して具体的な金額を提示しやすく、信頼感も高まります。特に、不動産売買では大きな金額が動くため、事前に費用感を共有しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
仲介手数料を精算するタイミングと流れ
仲介手数料の支払い義務は、原則として売買契約または賃貸契約が成立した時点で発生します。しかし、実際に支払うタイミングは契約内容によって異なるものです。
不動産売買では、契約書を締結した日と物件の引渡しが完了した日の2回に分けて、50%ずつ支払うケースが多く見られます。
一方、賃貸契約では、入居契約を結ぶ際に一括で支払うのが一般的です。契約内容によっては、手付金や中間金の支払いと同時に精算を求められる場合もあります。
近年普及が進んでいる電子契約を利用する場合でも、オンライン決済や銀行振り込みにより、同様のタイミングで精算手続きが行われます。トラブルを防ぐためにも、支払いの時期や方法は契約前にしっかり確認・合意しておくことが大切です。
不動産仲介の電子契約については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
⇒不動産仲介を電子契約で効率化する方法|流れやメリットデメリットも解説
仲介手数料を安くする場面
不動産仲介手数料は法律で上限が定められています。しかし不動産会社の判断によって、上限額より安く設定される場面もあります。
例えば、開業して間もない不動産会社が実績や顧客基盤を築くために、期間限定の「手数料割引キャンペーン」などを打ち出して集客するケースです。
また、顧客が複数の不動産会社に相談し相見積もりを取っている状況では、他社との差別化を図るために手数料の割引を提案することもあります。
さらに、同じ顧客が「自宅の売却」と「新居の購入」を同じ不動産会社に依頼する、いわゆる「住み替え」のケースでは、セットでの取引となるため、手数料が割引されることも少なくありません。
仲介手数料を高くしてよいケース
不動産仲介では、原則として宅地建物取引業法で定められた上限を超えて仲介手数料を受け取ってはいけません。ただし、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に上限を超える手数料を設定できるケースがあります。
その代表例が「低廉な空家等(価格が800万円以下の宅地・建物)の媒介の特例」です。
この特例では、上限を超えて最大33万円(税込)まで仲介手数料を受け取れます。適用には、依頼者へ内容を事前に説明した上で、同意が必要です。
さらに、2024年7月1日以降は買主側からも同額の手数料を受け取れるようになりました。
この制度が設けられた背景には、低価格の空き家や土地では仲介会社の利益が少なく、事業として成り立ちにくいという問題があります。特例は、不動産会社の経営を支援し、空き家の流通を促進するための措置です。
参照:国土交通省HP「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」
また、遠方への出張や特殊な調査など、通常の仲介業務の範囲を超える作業が発生した場合、事前に依頼者の同意があれば、その実費相当額を報酬として上乗せできます。
例えば、再建築不可物件の調査や、測量士・司法書士といった専門家の手配などがこれに該当します。
ただし、追加の報酬を受け取る際は、必ず事前に見積もりを提示しなければなりません。依頼者の承諾を得た上で、契約書や重要事項説明書への内容明記が必須です。
仲介手数料以外に不動産売買で必要な諸費用
不動産売買では、仲介手数料以外にもさまざまな諸費用が発生します。こういった費用の事前把握は、円滑な資金計画を立てる上で欠かせません。
ここでは、代表的な諸費用について解説します。
司法書士報酬やローン関連の手数料
不動産の所有権を移転する際は、法務局での登記手続きが必要であり、一般的には司法書士に依頼します。その際に支払う報酬は、5万~10万円前後が相場です。
また、買主が住宅ローンを利用する場合は、金融機関に支払う事務手数料や保証料、団体信用生命保険料などの費用が発生します。さらに、万が一の火災に備えて火災保険への加入も必須です。
これらの費用は、利用する金融機関や物件の条件によって異なります。総額を正確に把握するためにも、事前に見積もりで詳細を確認しておくのが望ましいでしょう。
登録免許税や印紙税などの税金
不動産の売買では、契約や登記に関わる複数の税金が発生します。
まず、不動産売買契約書に貼付する「印紙税」が必要です。印紙税は、成約価格が10万円を超える場合に課税されます。
平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成された契約書は軽減措置の対象で、契約金額に応じて以下の軽減税率が適応されます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万円を超え50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 | 500円 |
| 100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超過から1,000万円以下のもの | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円を超えるもの | 600,000円 | 480,000円 |
出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
次に、所有権移転登記や抵当権設定登記を行う際に「登録免許税」が課されます。この税額は、土地や建物の固定資産税評価額に基づいて算出されるものです。適用される税率も物件の種類や条件によって異なります。
特に、住宅ローンを利用して購入する場合には、借入額に応じた抵当権設定登記の登録免許税も加わるため、税負担全体を考慮した資金計画が不可欠です。
譲渡所得税など売却益にかかる税金
不動産の売却で利益(譲渡所得)が生じた場合、その金額に対して所得税・復興特別所得税・住民税が課されます。これらをあわせて、一般的に「譲渡所得税」と呼び、課税額は次の式で求められます。
課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
税率は不動産の所有期間によって大きく異なり、所有期間が5年以下なら「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」として区分されます。
| 所有期間 | 税金の種類 | 税率 |
| 短期譲渡所得(所有5年以下) | 所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(所有5年超) | 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315% | 20.315% |
つまり、長く保有した不動産を売却するほど、税負担が軽くなる仕組みです。
参照:国税庁「土地や建物を売ったとき」
一方で、売却によって損失が出た場合には、給与所得など他の所得と損益通算を行ったり、損失を翌年以降に繰り越して控除を受けたりする制度も利用できます。
不動産仲介の報酬に関するよくある質問
ここでは、不動産仲介の報酬に関するよくある質問を紹介します。
- Q1. 仲介手数料の値引き交渉はできますか?
- Q2. 契約がキャンセルになった場合、仲介手数料は返金されますか?
- Q3. 仲介手数料は誰が払うのですか?
- Q4. 仲介手数料に消費税はかかりますか?
- Q5. 仲介手数料の勘定科目は?
Q1. 仲介手数料の値引き交渉はできますか?
上限額は法律で定められていますが、下限はありません。そのため、不動産会社との交渉によって値引きが可能な場合もあります。
ただし、手数料を大幅に下げると広告費やサポート体制に影響が出る場合もあるため、値下げを求める際は理由を明確にし、納得のいく形で合意することが大切です。信頼できる不動産会社を選び、費用だけでなくサービスの質も重視しましょう。
Q2. 契約がキャンセルになった場合、仲介手数料は返金されますか?
仲介手数料は、売買や賃貸などの契約が正式に成立した時点で発生する成果報酬です。そのため、契約締結後に売主や買主、貸主や借主の都合でキャンセルになった場合でも、原則として仲介手数料は返金されません。
これは、不動産会社が契約成立までに広告掲載や案内、交渉などの業務をすでに行っているためです。
ただし、契約が停止条件付きで締結されており、条件が成就しなかった場合など、一部の例外では返金が行われるケースもあります。
契約が成立していない段階であれば手数料は発生しません。トラブルを防ぐためにも、契約前に「どの時点で発生するか」を仲介会社に確認しておきましょう。
Q3. 仲介手数料は誰が払うの?
不動産の仲介手数料を支払うのは、「仲介を依頼した人」です。売買契約の場合は、原則として売主と買主の双方が、それぞれ依頼した不動産会社へ支払います。
一方、賃貸契約では、貸主・借主のいずれか、もしくは両者で分担して支払います。負担割合は契約書や募集条件に明記されているため、契約前に必ず確認しておきましょう。認識の違いが後のトラブルにつながるため、事前の合意形成が重要です。
Q4. 仲介手数料に消費税はかかりますか?
仲介手数料には消費税が課されます。不動産会社が提供する「仲介」というサービス自体が課税対象の役務にあたるからです。請求される手数料額に消費税が上乗せされます。
例えば、1,000万円の物件の売買契約なら「1,000万円×3%+6万円=36万円」に消費税10%(2025年時点)が加算され、39万6,000円が仲介手数料の上限となります。
Q5. 仲介手数料の勘定科目は?
仲介手数料の勘定科目は、取引の内容によって異なります。
まず、オフィスや店舗などを賃貸契約で借りる場合は、支払う手数料を「支払手数料」として経費処理します。これは、仲介会社へのサービス利用料という性質を持つためです。
一方、不動産を購入する場合は、仲介手数料を「経費」ではなく、資産の取得原価の一部として扱います。具体的には、建物に関する手数料は「建物」の勘定科目に含めて計上します。
経理処理を誤ると税務上の問題が生じる可能性があるため、会計士や税理士に確認し、適切な勘定科目で処理することが望ましいでしょう。
不動産仲介の報酬を理解して運営しよう
不動産の仲介手数料とは、不動産会社が売買や賃貸の取引を仲介した際に受け取るサービスの対価です。
宅地建物取引業法によって上限が明確に定められており、売買の場合(400万円を超える物件)は「(売買価格×3%+6万円)+消費税」、賃貸の場合は「家賃1か月分+消費税」が一般的な目安となります。
仲介手数料は、契約が成立した時点で仲介を依頼した側が支払うのが原則です。また、売主と買主のどちらも同じ不動産会社に依頼している場合は、双方がそれぞれ手数料を負担します。
さらに、印紙税や登録免許税といったその他の諸費用も発生するため、取引全体のコストを見据えた資金計画が大切です。単に手数料の安さだけで判断せず、実績や信頼性の高い不動産会社を選ぶことが、安心・安全な取引につながります。
不動産仲介業務の効率化と顧客満足度の向上を目指すなら、ツールの活用も有効な手段です。
不動産コミュニケーションクラウド『Facilo(ファシロ)』は、物件提案や顧客管理といった日々の業務を大幅に効率化し、営業担当者が本来注力すべき顧客対応に集中できる環境を実現します。
ご興味のある方は、ぜひ一度資料をダウンロードしてみてください。
⇒Faciloのサービス資料をダウンロードする