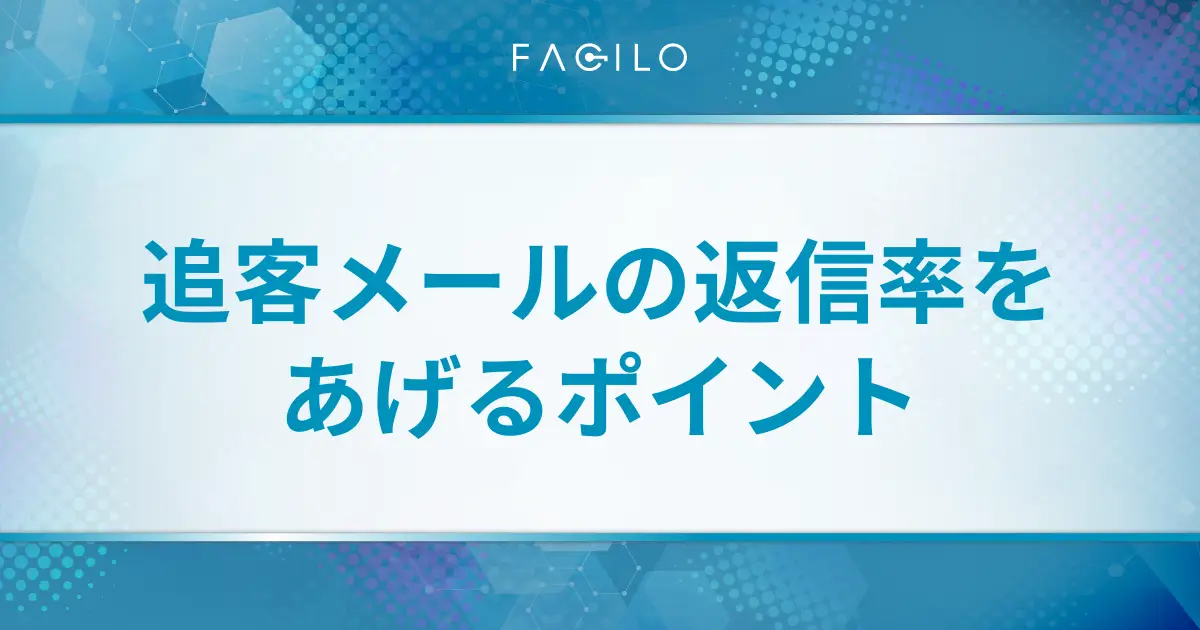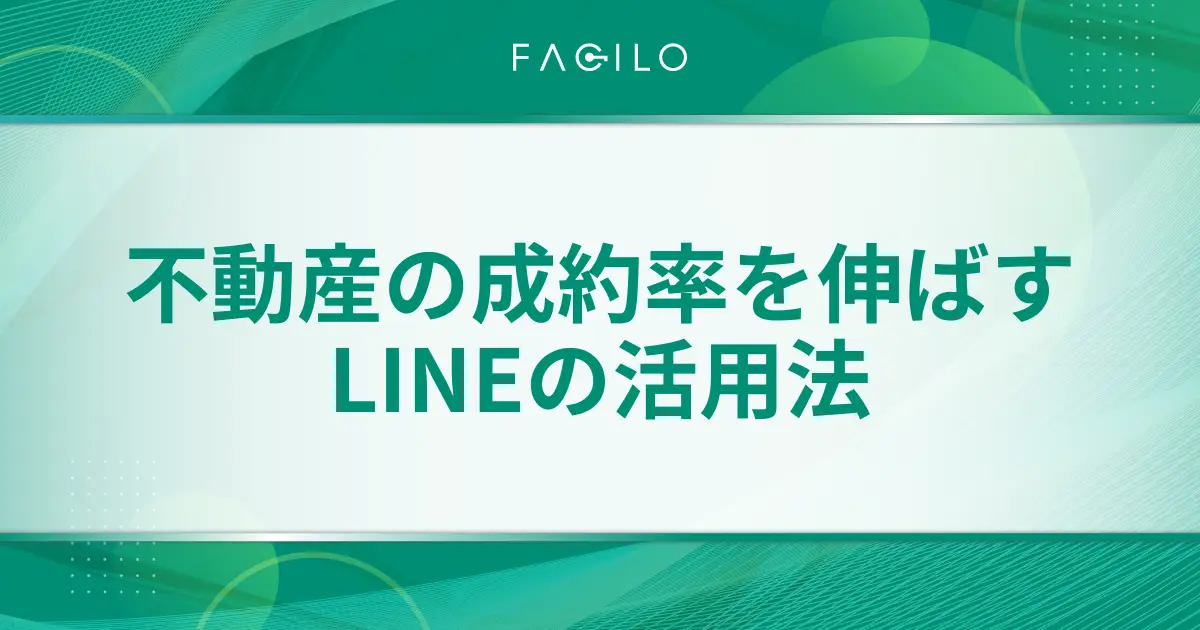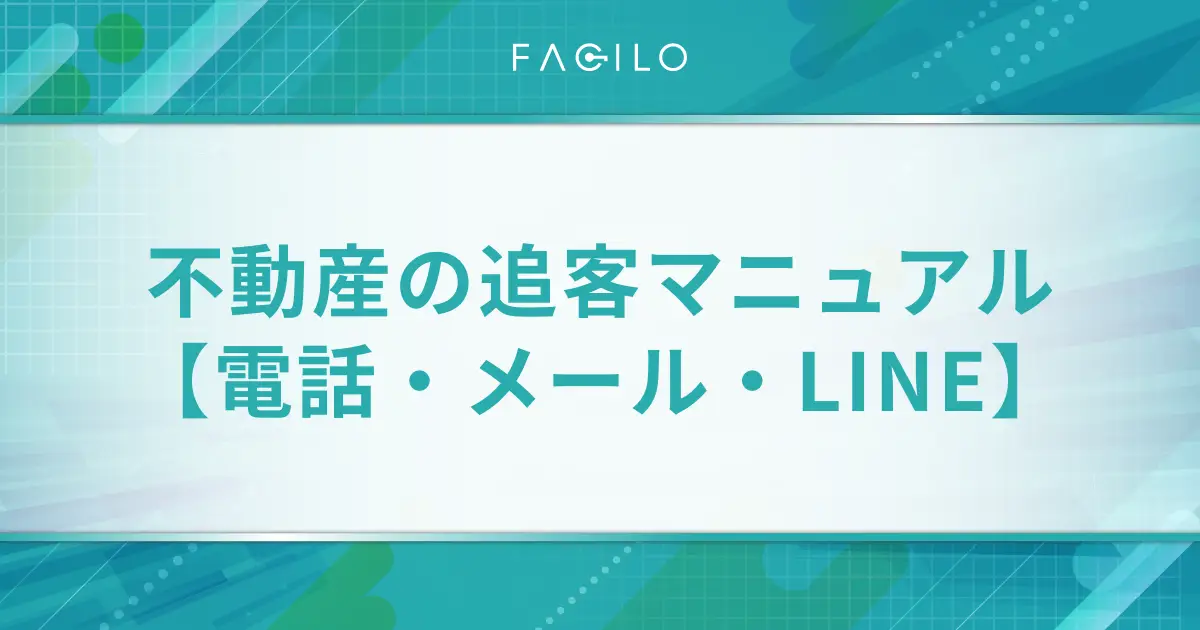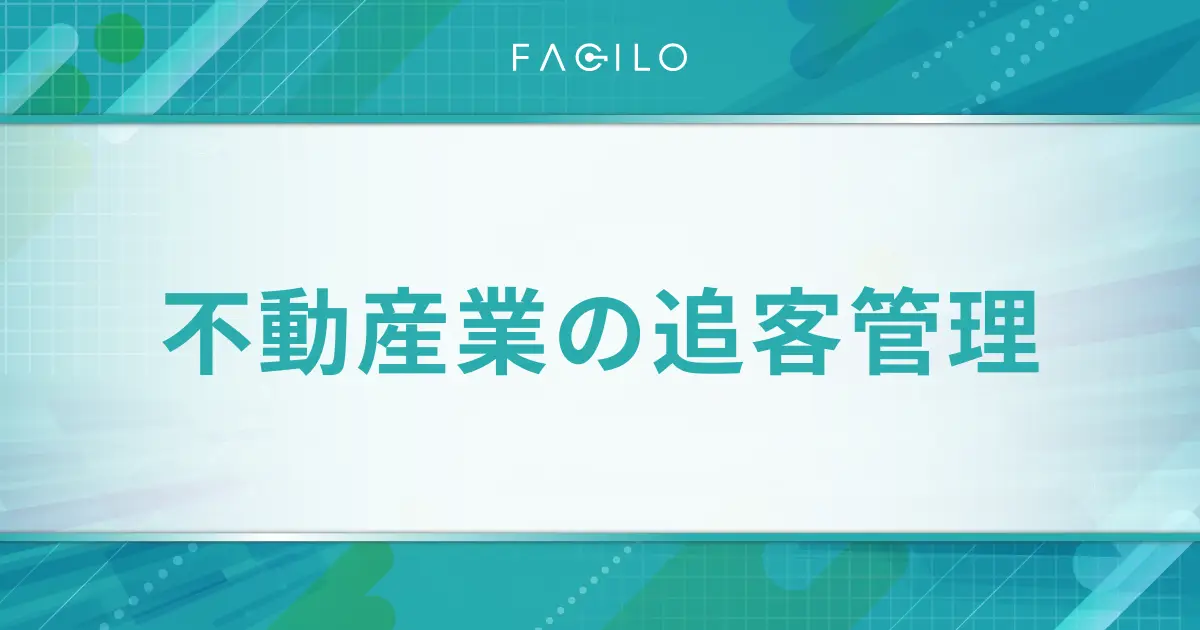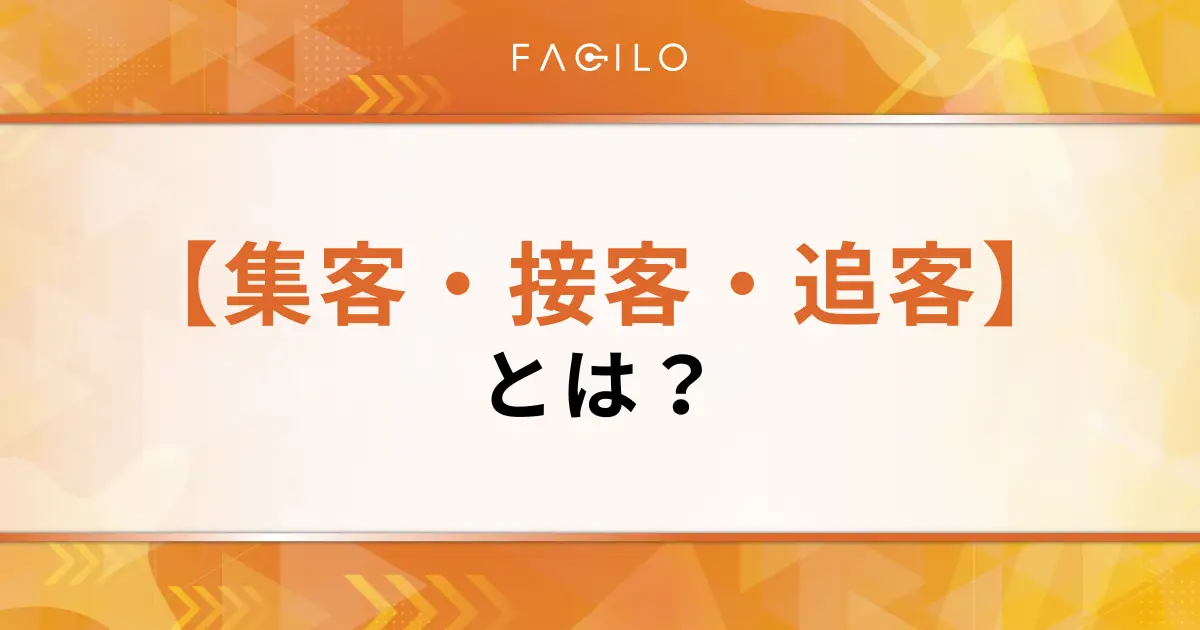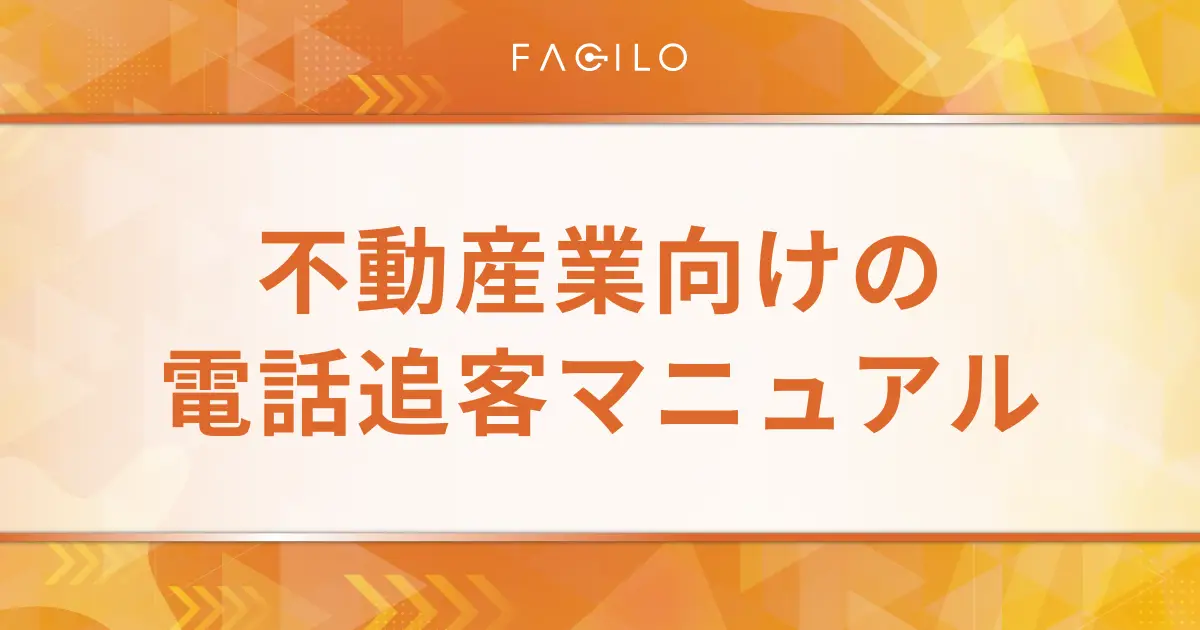
不動産開業で知っておきたい税金|個人事業と法人のメリット・デメリット

不動産業の開業を目指す際、個人事業主として始めるか、法人を設立するかで悩む人は少なくありません。どちらを選ぶかによって、税金の仕組みや手続きの負担、運営コストなどが大きく変わるため、違いをしっかり理解しておくことが大切です。
この記事では、不動産開業における個人事業主と法人の違いを、税金・費用・運営面からわかりやすく解説します。それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、自分に合った開業スタイルを選ぶための判断材料として、ぜひ参考にしてください。
1. 不動産業の税金は個人事業と法人で大きく異なる
不動産業を始めるにあたり、個人事業主としてスタートするか法人を設立するかは、事業運営だけでなく納める税金の種類や金額に大きな影響を与えます。
両者では適用される税法が異なるからです。所得の規模や事業の形によってどちらが有利になるかは変わります。そのため、税金に関する正しい知識を持つことが重要です。
項目 | 個人事業主 | 法人 |
適用される税金 | 所得税、住民税、事業税、消費税 | 法人税、法人住民税、法人事業税、消費税 |
税制 | 累進課税(所得に応じて5%~55%) | 比例税率(所得800万円以下は15%、超過分は23.2%) |
課税対象 | 事業所得(売上-経費) | 各事業年度の所得 |
個人事業主の場合は「所得税」が課され、所得が増えるほど税率の上がる累進課税が適用されます。
一方、法人の場合は「法人税」が課される仕組みです。税率が一定のため、利益が大きくなるほど税負担を抑えられる可能性があります。
2. 個人事業主と法人における税制や資金面の違い
個人事業主と法人では、税金の計算方法だけでなく、経費として認められる範囲や社会保険の扱い、金融機関からの信用力にも違いがあります。
項目 | 個人事業主 | 法人 |
経費の範囲 | 事業に直接関連する費用のみ | 役員報酬、退職金、福利厚生費など幅広く損金算入可能 |
加入する保険 | 国民保険(国民健康保険、国民年金) | 社会保険(健康保険、厚生年金保険) |
信用力や融資の受けやすさ | 個人に依存するため、法人より低い | 個人事業主より融資を受けやすく、多様な資金調達が可能 |
これらの違いを理解し、自身の事業計画に合った形態を選びましょう。
経費計上範囲と損金算入
経費として認められる範囲は、法人の方が広い傾向にあります。
項目 | 個人事業主 | 法人 |
経費の範囲 | 事業に直接関連する費用のみ | 役員報酬、退職金、福利厚生費など幅広く損金算入可能 |
給与 | 自身への給与は経費にできない | 役員報酬として経費計上可能 |
生命保険料 | 所得控除(上限あり) | 種類により全額または一部を損金算入可能 |
個人事業主の場合、事業と私生活の支出の区別が曖昧になりがちで、事業関連性が明確でないと経費として認められません。
一方、法人では役員報酬や社宅、福利厚生費など、個人事業主では経費にしにくい費用も損金として算入でき、節税の選択肢が広がります。
特に、役員報酬を調整することで法人の利益をコントロールし、法人税と個人の所得税のバランスを最適化できるのは、法人ならではの大きなメリットです。
事業規模が大きくなるほど、法人化による節税メリットは大きくなります。
社会保険と将来の年金受給額の違い
社会保険の加入義務も、個人事業主と法人で異なります。
項目 | 個人事業主 | 法人 |
加入する保険 | 国民保険(国民健康保険、国民年金) | 社会保険(健康保険、厚生年金保険) |
保険料負担 | 保険料負担 | 会社と従業員で折半 |
将来の年金 | 国民年金(基礎年金)のみ | 国民年金に加え、厚生年金が上乗せされる |
個人事業主として開業する場合は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。国民健康保険料は、所得や年齢、住んでいる市区町村によって金額が異なるので注意が必要です。
また、国民年金は将来受け取れる年金額が比較的少ない点にも留意してください。
一方、法人は厚生年金と健康保険への加入が義務付けられており、保険料の半分を会社が負担します。従業員だけでなく、経営者自身も厚生年金に加入できるため、将来受け取る年金額は国民年金よりも手厚くなるでしょう。
従業員の福利厚生という観点でも、社会保険に加入できる法人の方が魅力的であり、人材確保の面で有利に働きます。
信用力と融資の受けやすさの差
事業を継続・拡大していく上で、資金調達は欠かせない要素です。一般的に、金融機関からの信用力は法人の方が高いとされています。
項目 | 個人事業主 | 法人 |
社会的信用力 | 個人に依存するため、法人より低い | 高い |
資金調達 | 融資限度額が低くなる傾向がある | 融資を受けやすく、多様な資金調達が可能 |
取引 | 大企業との取引で不利になる場合がある | 大企業との取引で不利になる場合がある |
個人事業主の融資審査では、事業主本人の個人資産や保証能力が重視される傾向にあります。そのため、借入できる金額は限られるのが実情です。
一方で、法人は登記によって社会的な存在が公に証明されており、会計処理も厳格におこなわれるため、事業の透明性が高いと評価されます。そのため、融資審査で有利に働き、より大きな金額を借り入れできる可能性が高いです。
さらに、大手企業との取引や公共事業への入札など、法人でなければ参入が難しいビジネスチャンスも広がります。
3. 不動産開業を個人事業で始めるメリット
法人に比べて信用力や節税面で不利な点がある一方で、個人事業主には手軽に始められるというメリットがあります。
ここでは、不動産開業を個人事業で始める利点を詳しく見てみましょう。
開業手続きが簡単にできる
個人事業主として開業する際の手続きは非常にシンプルです。税務署に「開業届」を提出するだけで、すぐに事業をスタートできます。
法人のように、法務局への登記や定款の作成・認証といった複雑で時間のかかる手続きは必要ありません。将来的に法人化を目指す場合でも、まずは個人事業として実績を積み、タイミングを見て法人へ移行することが可能です。
そのため、副業で不動産仲介を始めたい方や、できるだけ早く事業を立ち上げたい方にとって、個人事業主としての開業はおすすめの選択肢といえます。
初期費用を抑えやすい
開業時のコストを大幅に抑えられるのも、個人事業主として開業する大きなメリットです。
法人を設立する場合、定款認証や登記手続きなどに費用が発生し、株式会社なら約20万円以上、合同会社でも10万円前後の初期費用が必要になります。一方、個人事業主であれば、資本金や設立費用は不要です。
事務所の賃貸費用や宅建業免許の申請費用など、実務に必要な費用へ資金を集中できます。初期リスクを抑えて少ない自己資金で開業を目指せるでしょう。
利益が少ない場合は税負担が少ない
個人事業主にかかる所得税は、所得が多いほど税率が上がる累進課税制度が採用されています。開業初期などで所得が少ない場合は、法人税よりも低い5%からの税率が適用され、税負担を抑えやすいのが特徴です。
さらに、青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除や、赤字を3年間繰り越せる制度などの優遇措置も受けられます。
開業当初は利益が安定しないことも多いため、税負担が少ないのは経営を続ける上で大きな支えとなります。これらの制度は、小規模での開業や副業として不動産事業を始めたい方にとっても有利といえるでしょう。
高収入を目指せる
不動産仲介の報酬は、成約した物件価格に応じた成功報酬が基本です。そのため、自身の努力や営業スキルが直接収入に結びつきます。
個人事業主の場合、得られた利益はすべて自分のものになるため、頑張り次第で会社員時代の収入を大きく上回ることも夢ではありません。
法人と違って役員報酬の上限などを気にする必要がなく、成果がダイレクトに収入に反映される点は、大きなモチベーションにつながります。
4. 不動産開業を個人事業で始めるデメリット
手軽に始められる個人事業主ですが、事業が成長していくにつれて、税金や信用の面でデメリットが目立ってくるケースもあります。将来的な事業拡大を視野に入れている場合は、これらの点を十分に理解しておきましょう。
所得税課税で利益規模によって税率が上がる
個人事業主のメリットであった累進課税は、所得が増えると逆にデメリットになります。
所得が高くなるにつれて税率も上昇し、最高税率は45%に達します。これに住民税(約10%)を加えると、所得の半分以上を税金として納めることに。
利益が大きくなると法人税の方が税率は低くなるため、ある程度の所得を超えた段階で法人化を検討するとよいでしょう。
赤字繰越は3年までと短く制限される
青色申告をしている個人事業主は、事業で生じた赤字を翌年以降の黒字と相殺できます。その繰越期間は最長で3年間です。なお、白色申告では、過去の赤字は繰り越せず、黒字と相殺できません。
一方、法人の場合は赤字を10年間繰り越すことが可能です。不動産業は、景気の波や大型案件の有無によって年間の収益が大きく変動することもあります。赤字が数年にわたって続くような不測の事態が起きた場合、繰越期間が短い個人事業主は不利になる可能性があるのです。
社会保険に加入できない
個人事業主は、会社員のように健康保険や厚生年金などの社会保険に加入できません。その代わりに、国民健康保険と国民年金へ加入する形になります。
保険料の負担は所得によって変動し、一般的に法人が加入する健康保険に比べて、病気や怪我で働けなくなった際の傷病手当金などの保障が手薄です。また、将来受け取れる年金額も厚生年金より少なくなるため、老後への備えは別途個人で準備する必要があります。
さらに、従業員を雇う場合も注意が必要です。個人事業主では原則として社会保険の適用事業所にならないため、従業員を社会保険に加入させることができません。
このため、福利厚生面で法人より見劣りする可能性があり、人材採用や定着に不利になるケースもあります。
法人に比べると融資や信用力で不利になる
個人事業主は、事業と個人の区別が曖昧なため、法人に比べて社会的な信用力が低いとみなされる傾向があります。
金融機関から融資を受ける際には、事業計画や将来性だけでなく、事業主本人の資産や信用情報まで厳しく審査されるでしょう。また、法人のように決算書や財務基盤が整っていない場合も多く、結果として希望した融資額を満額で受けられないケースも少なくありません。
さらに、取引先や顧客からの信頼面でも法人より不利になる場合があります。特に、大口取引や企業間の提携などでは、法人格を持たないことが契約上のリスクと判断されるケースもあり、ビジネスチャンスを逃す可能性がある点はデメリットといえるでしょう。
5. 不動産開業を法人でおこなうメリット
初期費用や手続きの煩雑さはあるものの、法人の設立で得られるメリットは数多くあります。
ここでは、法人化のメリットについて詳しく解説します。
税金面での優遇を受けやすい
最大のメリットの1つが、税制上の優遇です。法人税の実効税率は最大でも23.2%と、個人の所得税の最高税率(45%)に比べて低く設定されています。
特に、所得が800万円以下の部分には15%の軽減税率が適用されるため、利益が大きくなるほど個人事業主よりも税負担を大幅に抑えられます。また、役員報酬や退職金を経費として計上できるなど、節税の選択肢が豊富です。
10年の赤字繰越ができる
法人の場合、事業で発生した赤字(欠損金)を最長10年間繰り越して、将来の黒字と相殺できます。これは、個人事業主が最大3年間しか繰り越せないのに比べて、大きなメリットといえるでしょう。
不動産業のように、景気や市況によって収益が変動しやすい業種では、この制度が経営を安定させる支えになります。赤字の出た年があっても、将来の黒字で税負担を軽減できるため、長期的な視点で経営計画を立てられるのが法人化の大きな利点です。
事業を拡大しやすい
法人化すると、社会的な信用力が高まり、経営基盤を強化しやすくなります。法人登記によって事業の透明性が認められれば、金融機関からの融資や資金調達もスムーズに行えるでしょう。
さらに、事務所の賃貸契約や大手企業との取引など、信頼性が求められるシーンでも法人格は有利です。あわせて、法人は社会保険制度を整えやすいため、求職者からの信頼を得やすく、優秀な人材を採用しやすいという強みもあります。
このように、資金調達・取引・人材確保のすべてで信用力が向上することから、事業の拡大を見据えるなら法人化が有利といえるでしょう。
社会保険に加入できる
法人は、従業員の人数にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務となっています。
保険料は会社と従業員で折半する仕組みのため、従業員の負担を軽減しつつ福利厚生を充実させることが可能です。これにより、従業員の満足度や定着率の向上にもつながるでしょう。
もちろん、経営者自身も厚生年金に加入できます。個人事業主が加入する国民年金や国民健康保険に比べて手厚い保障を受けられ、将来の年金額も増えるというメリットを享受できるのです。
個人へのリスクが回避できる
株式会社や合同会社などの法人は「有限責任」が法律で定められています。
これは、もし事業がうまくいかず負債を抱えた場合でも、経営者は出資した金額の範囲内でのみ責任を負うという仕組みです。そのため、個人の貯金や自宅などの私有財産が差し押さえられることは原則ありません。
一方、個人事業主は「無限責任」で、事業の負債をすべて個人で負う必要があります。この点で、法人化すればリスクを限定できるため、大きな事業投資や融資を検討する上での安心材料となるでしょう。
6. 不動産開業を法人でおこなうデメリット
多くのメリットがある法人設立ですが、もちろんデメリットも存在します。特に、設立と維持にかかるコストは、個人事業主と比べて高くなる傾向です。
これらの負担を理解した上で、法人化のタイミングを慎重に判断しましょう。
設立費用や維持コストが個人より高い
法人を設立するには、定款の認証手数料や登記費用などの初期費用が発生します。
株式会社であれば最低でも約20万円、合同会社でも約10万円が必要です。さらに、司法書士などの専門家に手続きを依頼すれば、別途報酬がかかります。
また設立後も、法人ならではの維持コストが発生します。例えば、税務申告が複雑になるため税理士への顧問料が必要になったり、社会保険料の会社負担分が増えたりと、個人事業主にはないコストが増加するでしょう。
赤字でも税金がかかる
個人事業主の場合、赤字であれば所得税や住民税はかかりません。一方、法人の場合は、たとえ事業が赤字でも「法人住民税の均等割」という税金を納めなければなりません。
この税額は資本金の額や従業員数によって決まり、最低でも年間約7万円程度の負担が生じます。さらに、事業規模や資本金が大きくなるほど均等割の金額も増加する仕組みです。
利益が出ていなくても必ず支払う必要があるため、開業当初の資金繰りを圧迫する要因になりえます。
社会保険への加入が義務である
法人化のメリットでもある社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は、裏を返せばコスト増につながるデメリットにもなります。
法人は、たとえ社長一人であっても社会保険への加入が法律で義務付けられています。保険料は会社と個人で折半しますが、事業主にとってはこれまでなかった固定費が増えることに。
さらに、従業員を雇用すれば人数に応じて会社の負担額も増加します。そのため、給与だけでなく社会保険料も含めた総人件費を見据えて、計画的に資金計画を立てることが欠かせません。
7. 不動産開業は個人事業と法人のどちらがおすすめか
ここまで見てきたように、個人事業主と法人にはそれぞれメリットとデメリットがあります。どちらを選ぶべきかは、事業計画や将来のビジョンによって異なるものです。
次の比較表を参考に、自分にとって最適な形を選択しましょう。
項目 | 個人事業主 | 法人 |
設立手続き | 開業届の提出のみで簡単 | 定款認証や登記が必要(10万〜30万円) |
税制 | 累進課税(所得に応じて5%~55%) | 比例税率(所得800万円以下は15%、超過分は23.2%) |
赤字繰越 | 最大3年 | 最大10年 |
社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(加入義務あり) |
信用力・融資 | 個人に依存し、審査が厳しい傾向 | 信用力が高く、融資を受けやすい |
初期費用 | 安く抑えられる | 設立・維持コストが高い |
適したケース | 小規模開業、低リスクで始めたい人 | 事業拡大志向、高収益・信用力重視の人 |
個人事業がおすすめのケース
個人事業主が向いているのは、次のような人です。
開業費用を抑えて、まずは小規模からスタートしたい
副業や個人でリスクをできるだけ減らしながら不動産業に挑戦したい
開業初期の利益が少なく、税負担を軽くして様子を見たい
手続きの手間を減らし、とにかく早く事業を始めたい
まずは1人でコツコツと実績を積んでいきたい方には、最適な選択といえるでしょう。
法人がおすすめのケース
以下のような人は、法人設立がおすすめです。
複数店舗の展開や人材採用を進め、事業を大きく成長させたい
高い収益が見込め、法人税の優遇など税制メリットを活かしたい
金融機関からの融資を受けやすくし、取引先からの信頼性を高めたい
社会保険や福利厚生を整え、従業員を雇って安定した経営体制を築きたい
安定した経営基盤を築き、不動産ビジネスで大きな成功を目指す方は、法人化を検討するとよいでしょう。
8. 不動産開業の税金に関するよくある質問
ここでは、不動産開業の税金に関するよくある質問を紹介します。
Q1.不動産開業は、どのくらいの所得から法人化を検討すべきですか?
Q2.不動産を個人事業主として始めるデメリットはありますか?
Q3.個人事業主として始めた後に、法人化することは可能ですか?
Q1.不動産開業は、どのくらいの所得から法人化を検討すべきですか?
一般的に、課税所得が800万円から900万円を超えるあたりが、法人化を検討する1つの目安とされています。これは、個人の所得税率が法人税率を大きく上回るようになるラインだからです。
ただし、これはあくまで目安であり、経費にできる範囲や社会保険料の負担、将来の事業拡大の意向などを総合的に考慮して判断することが重要です。
Q2. 不動産を個人事業主として始めるデメリットはありますか?
個人事業主として不動産業を始める場合、社会保険に加入できないため保障が限定的です。事業と個人の区別が曖昧なことから信用力が低く見られやすい傾向にあり、融資の審査や大口の取引で不利になるケースもあります。
さらに、事業の負債をすべて個人で負う「無限責任」となるため、リスクを抱えやすい点も注意が必要です。また、赤字を繰り越せる期間が3年と短く、税務上の柔軟性にも限りがあります。
初期費用を抑えて小規模に始めるには適していますが、将来的な事業拡大を目指す場合は慎重な検討が求められるでしょう。
Q3.個人事業主として始めた後に、法人化することは可能ですか?
可能です。まずは個人事業主として小さく始め、事業が軌道に乗って利益が安定してきた段階で法人化する、いわゆる「法人成り」は一般的な流れです。
個人事業時代の売上実績や経営履歴は、法人設立後の融資審査などでもプラス評価となる場合があります。ただし、法人化の際には資産や契約の引き継ぎ、許認可の再申請など、専門的な手続きが必要です。税理士などの専門家に相談しながら進めると安心でしょう。
9. 不動産業の開業は税金をよく考えて始めよう
不動産業での独立開業は、大きな可能性を秘めています。しかし成功のためには事業計画だけでなく、税金に関する正しい知識が不可欠です。個人事業主としてスタートするのか、法人を設立するのか。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の事業規模や将来の方向性に合った形態を選ぶことが重要です。
特に開業当初は、顧客管理や物件提案、契約手続きなど、やるべきことが山積みになります。限られたリソースの中で効率的に業務を進めるためには、ITツールの活用が欠かせません。
不動産コミュニケーションクラウド「Facilo(ファシロ)」は、顧客とのやり取りや提案・進捗を一元管理できるツールです。誰でも効率的に成果の出せる仕組みづくりをサポートします。
スムーズな開業を実現するために、まずはFaciloの資料をダウンロードして導入を検討してみてはいかがでしょうか?