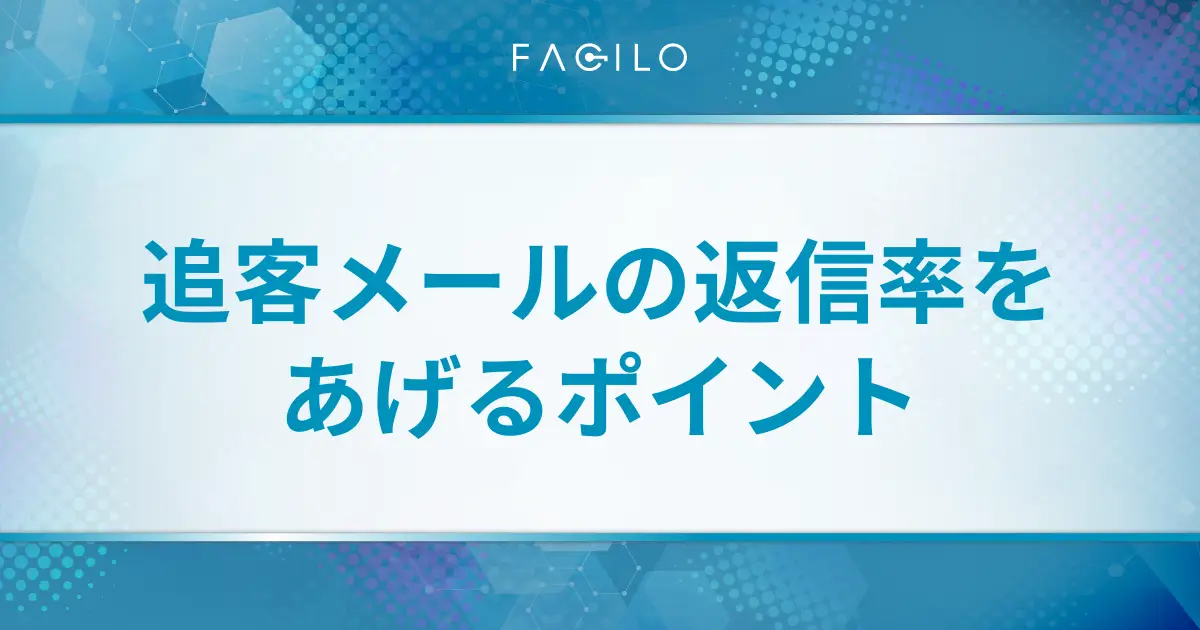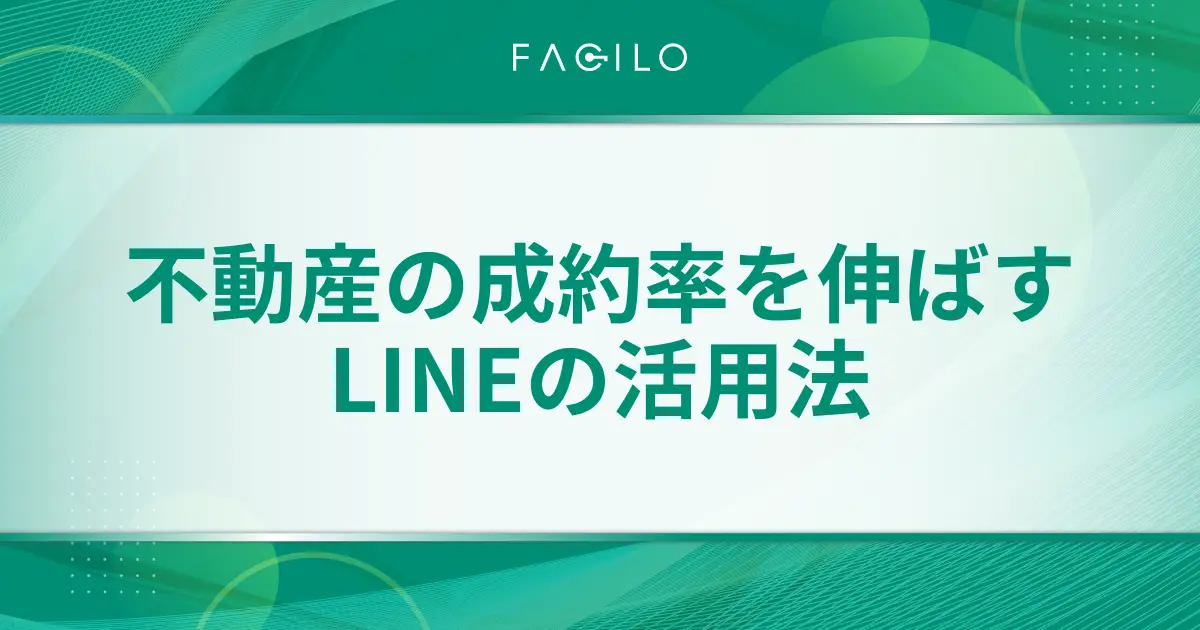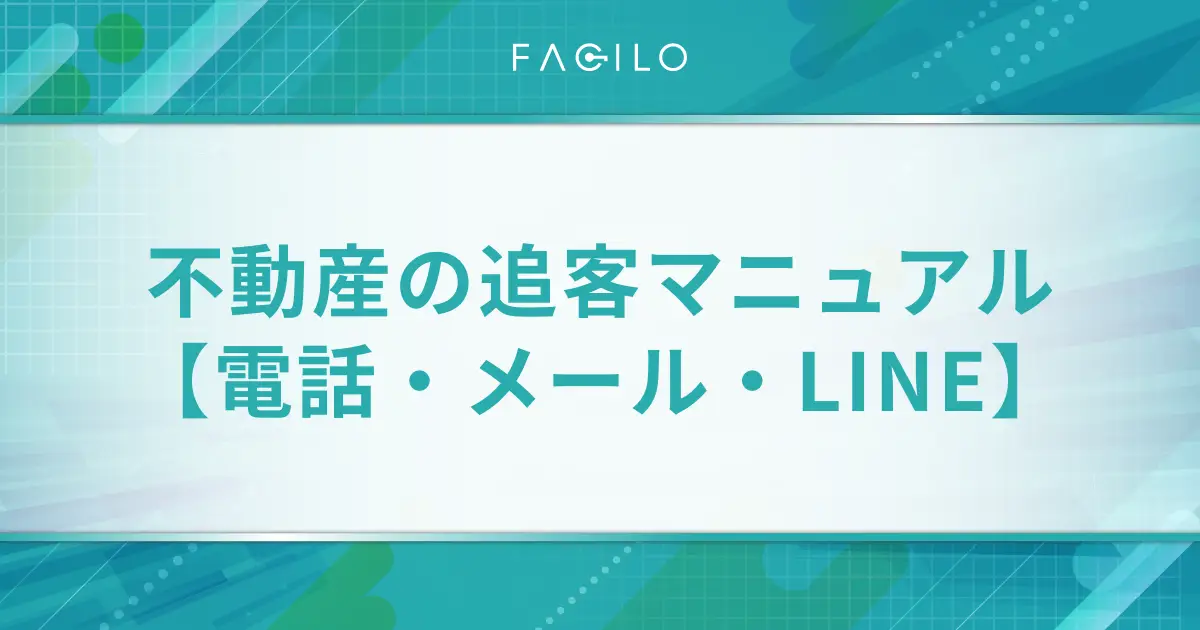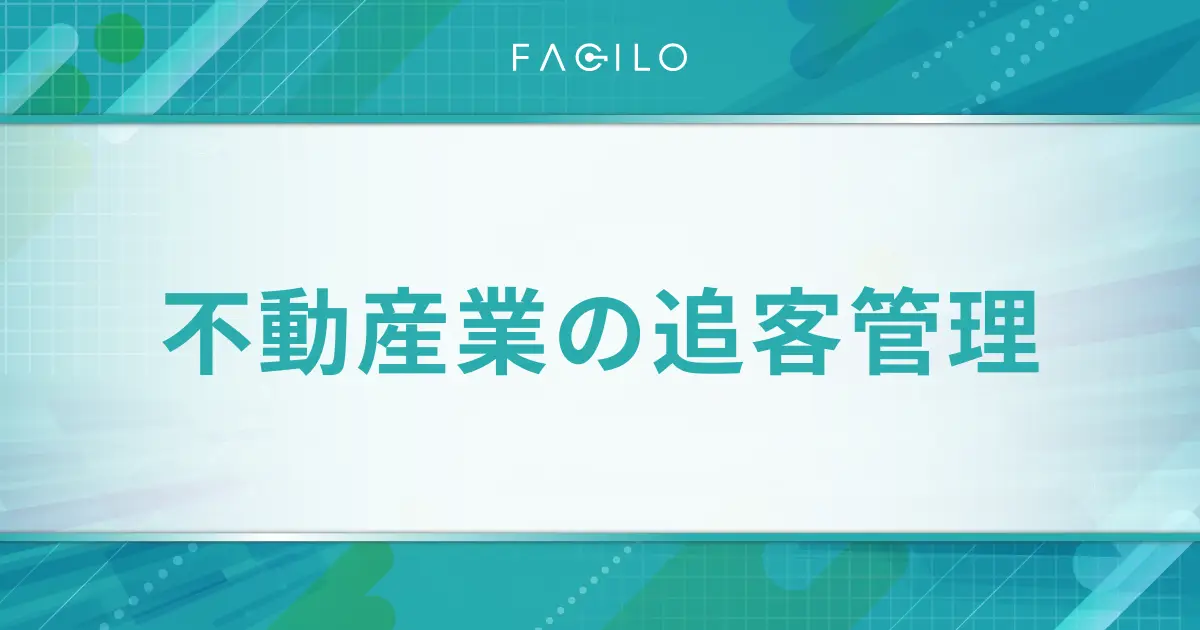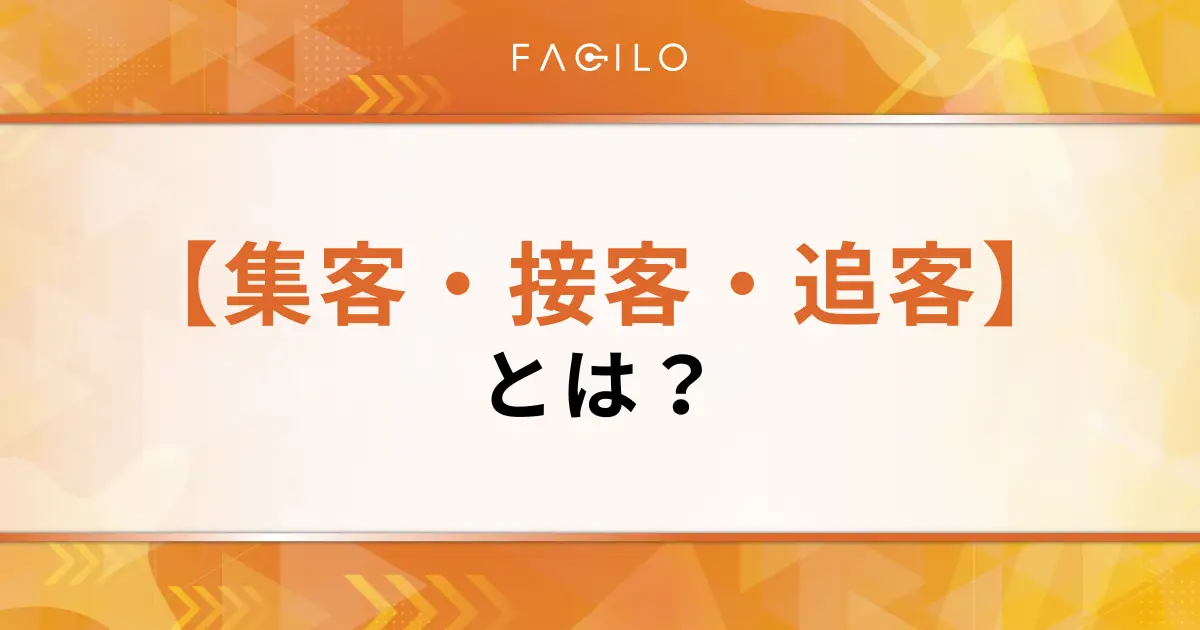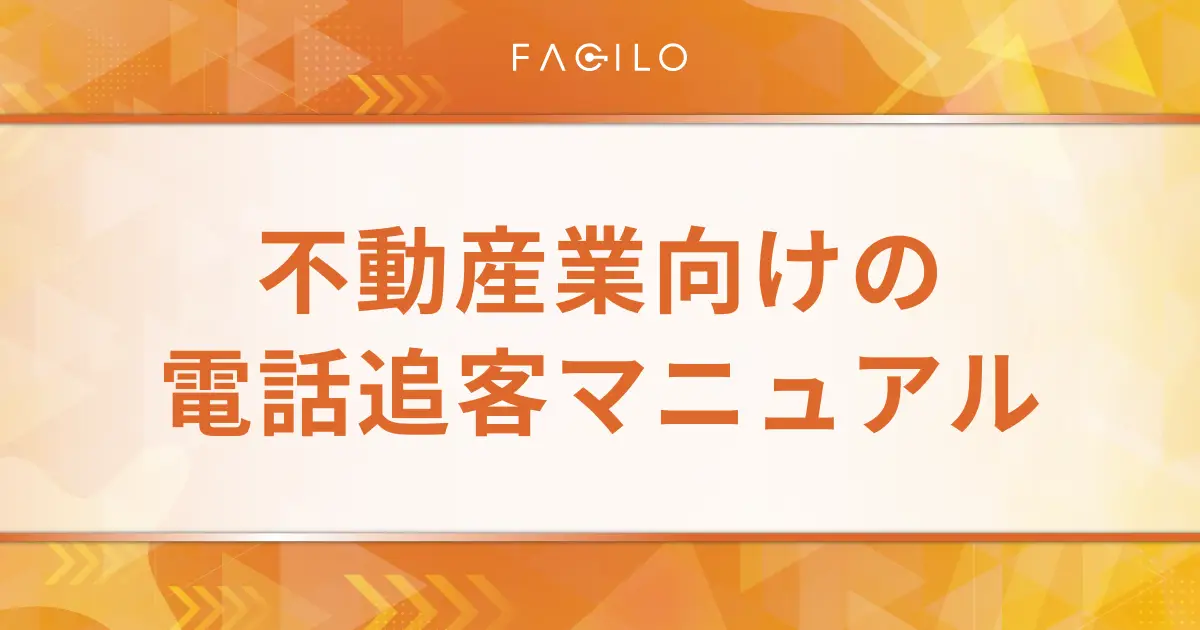
【一覧表付】不動産の開業の流れ!失敗しないポイントも解説
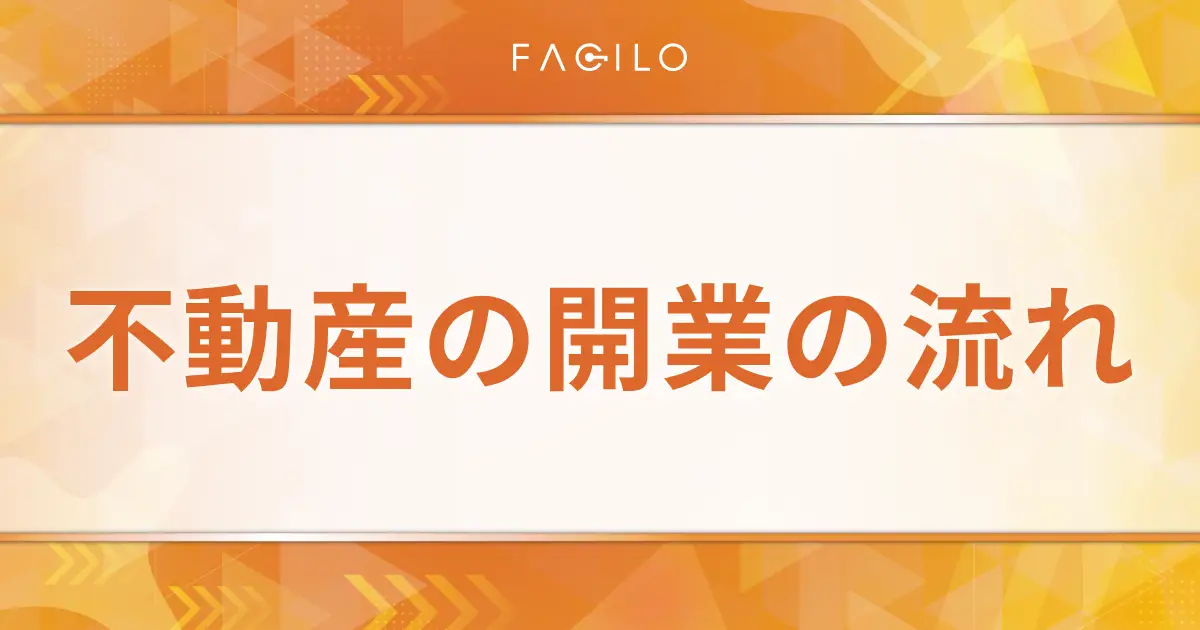
不動産の開業はチャンスが大きい一方、資金準備・事務所の設置・宅建業免許の取得など、踏むべき手続きが多くあります。それぞれの手続きには法律上の条件や注意点があるため、全体の流れをしっかり把握して進めることが大切です。
この記事では、不動産開業までの具体的な流れをわかりやすく解説。開業資金の準備から、失敗を防ぐポイント、業務を効率化する最新のDXツールなど、開業を成功へ導くための実践的な情報を詳しく紹介します。
1. 不動産開業の流れ【一覧表】
不動産開業は、全体の流れを把握し、計画的に進めることが大切です。以下の表では、開業までに必要なステップを整理しています。まずは、開業の全体像をイメージしましょう。
開業ステップ | 主な内容 | ポイント |
①方針の決定 | 経営形態や業種を選ぶ | 将来の事業規模や資金計画を見据えて検討する |
②資金の準備 | 開業費用・運転資金を確保する | 自己資金+融資・助成金を組み合わせるのが現実的 |
③事務所の設置 | 独立性があり常時使用できる事務所を準備 | 自宅・レンタルオフィス利用も可だが、法的要件に注意 |
④会社の設立 | 個人事業:開業届提出/法人:定款認証・登記 | 法人化は信用力や融資面、税制で有利になる場合も |
⑤各種手続き | 宅建士の配置、宅建業免許申請、保証協会加入 | 宅建士は必須。免許は5年ごとの更新が必要 |
⑥開業 | 広告・集客を開始し、営業スタート | 地域密着+DX活用で効率的な集客を目指す |
ここから、各ステップについて詳しくみていきます。
2. 不動産開業の流れ ①方針の決定
不動産開業における最初のステップは、事業方針を決めることです。どのような形態で経営し、どの業種を専門にするかによって、必要な手続きや準備内容が大きく変わります。
経営形態
まず、経営形態として、個人事業主として始めるか、法人を設立するかを決めます。
それぞれの特徴を以下にまとめました。
項目 | 個人事業主で開業 | 法人で開業 |
開業手続き | 税務署に「開業届」を提出するだけ。手続きが簡単でスピーディ。 | 定款作成・認証、登記などの手続きが必要。設立に時間と手間がかかる。 |
法人設立費用 | なし(個人事業) | 20万〜30万円(法人:定款認証料・登録免許税・専門家報酬など) |
税金の仕組み | 累進課税(所得に応じて5%~55%) | 比例税率(所得800万円以下は15%、超過分は23.2%) |
利益の扱い | 事業の利益はそのまま個人の所得になる。 | 会社の利益と個人の所得が分離。役員報酬や配当として受け取る。 |
節税・経費 | 経費計上の範囲が限られる。節税効果は限定的。 | 役員報酬や退職金なども経費にでき、節税の幅が広い。 |
信用力や融資の受けやすさ | 個人に依存するため、法人より低い。 | 個人事業主より融資を受けやすく、多様な資金調達が可能。 |
向いている人 | 小規模で始めたい人、まずは副業で開業をしたい人。 | 将来的に事業を拡大したい人、融資や採用を考えている人。 |
個人事業主の場合は、税務署に「開業届」を提出するだけで事業を始められます。手続きがシンプルで初期費用も抑えられるため、短期間で事業をスタートしたい方や、小規模で試しながら始めたい方に向いているでしょう。
一方、法人(株式会社など)は、定款の認証や設立登記が必要で、設立費用もかかります。その分、社会的信用力が高まり、銀行融資を受けやすくなるほか、税制面で有利になる場合も。将来的に事業を拡大したい場合は、法人化を検討するのがよいでしょう。
業種形態
次に、不動産業の中でどの分野を主軸にするかを決めます。主な業種形態には「売買仲介」「賃貸仲介」「管理業務」などがあります。
業種形態 | 業務内容や特徴 |
売買仲介 | ・土地や建物の売買を仲介 |
賃貸仲介 | ・アパートやマンションなどの賃貸物件を仲介 ・売買に比べて一件あたりの手数料は低いものの、比較的短期間で契約に至りやすく、安定した収入を積み重ねやすい |
管理業務 | ・物件オーナーに代わって、入居者募集や家賃回収、建物メンテナンスなどを行う ・継続的に管理手数料を得られるため、安定した収益を確保しやすい |
ご自身の経験や強み、そして開業するエリアの市場ニーズをしっかり分析し、最も適した業種を選ぶことが成功への近道です。
3. 不動産開業の流れ ②資金の準備
不動産開業には、まとまった資金が必要です。資金は大きく「開業費用」と「運転資金」の2つに分けられます。
計画段階で必要な金額を把握し、余裕のある資金計画を立てましょう。
開業費用
開業費用は、事業をスタートするために最低限必要な初期投資です。
開業費用の主な内訳は、宅建業免許の申請料や保証協会への加入金、事務所の賃貸・設備費用などが挙げられます。さらに、法人として開業する場合は、定款認証や登記費用として10万〜30万円が必要です。
項目 | 費用の内容 | 金額の目安 |
宅建業免許申請料 | 都道府県知事免許 | 3万3,000円 |
国土交通大臣免許 | 9万円 | |
保証協会への加入金 | 入会金、弁済業務保証金分担金など(協会や地域により変動) | 130万円〜180万円 |
事務所の開設費用 | 賃料、敷金・礼金、内装工事費 | 100万円〜300万円 |
デスクやPC、複合機などの備品 | 20万円〜100万円 | |
回線工事・初期設定費 | 5万円〜10万円 | |
法人設立費用 | 定款認証料、登録免許税、司法書士への報酬など | 10万円〜30万円 |
広告宣伝費 | 会社Webサイト制作、名刺、チラシ作成など | 10万円〜20万円 |
不動産開業には、おおよそ400万~1,000万円程度の資金が必要といわれています。ただし、金額は経営形態(個人・法人)や業種、開業する地域によって大きく異なるでしょう。
運転資金
運転資金とは、開業後の事業運営を安定させるために必要な経費のことです。
主に、事務所の家賃や光熱費、通信費など売上に関わらず毎月発生する固定費に加え、従業員の人件費や広告掲載料などの変動費も含まれます。
運転資金の目安は次のとおりです。
項目 | 費用の内容 | 金額の目安(月額) |
事務所家賃 | オフィスの賃料 | 10万円〜30万円 |
人件費 | 従業員を雇用する場合の給与 | 25万円~ |
水道光熱費・通信費 | 電気、水道、ガス、インターネット、電話代など | 3万~5万円 |
広告宣伝費 | 不動産ポータルサイト掲載料、Web広告費など | 10万円〜20万円 |
その他経費 | 交通費、交際費、事務用品費など | 5万円〜10万円 |
開業直後は売上が安定しにくいため、最低でも3〜6か月分の運転資金を確保しておくと安心です。開業前にしっかりと資金計画を立てておくことで、資金繰りに余裕を持ちながら安定した経営をスタートできます。
不動産の開業費用に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
⇒不動産業の開業費用を解説!必要資金は400万円〜?運営コストも紹介
4. 不動産開業の流れ ③事務所の設置
不動産開業は、宅地建物取引業法で定められた要件を満たした「事務所」の設置が義務づけられています。これは単なる作業スペースではなく、宅建業免許を取得するための必須条件です。
事務所として認められるためには、宅建業の業務を日常的に行える環境と設備が整っていること、社会的にも独立した事務所として認められる状態であることが求められます。具体的には、次のような条件が必須です。
他の事業や住居部分と明確に区分された独立した空間
専用の出入口がある
応接スペースが設けられている
従業員のデスクや椅子などの業務設備がある
固定電話が設置されている
参照:東京都住宅政策本部「東京都宅地建物取引業免許申請の手引」
近年は、自宅やレンタルオフィス、コワーキングスペースを事務所として利用するケースも増えています。ただし、その場合も上記の独立性要件を満たさなければなりません。特に、自宅の一室を使う場合は、居住スペースを通らずに直接入室できる構造であることがポイントです。
また、事務所の立地は顧客のアクセスや信頼性に大きく関わります。人通りの多いエリアや駅近など、来客しやすい場所を選び、看板や内装を整えることで集客効果も高まるでしょう。
5. 不動産開業の流れ ④会社の設立
事業方針が決まり資金の準備ができたら、次は会社の設立手続きに進みます。経営形態として「個人事業主」と「法人」のどちらを選んだかによって、手続きが異なります。
個人事業主
個人事業主として開業する場合、手続きは非常に簡単です。事業を始めてから1か月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出するだけで完了します。
この手軽さと、初期費用を抑えられる点が個人事業主として始める大きなメリットです。ただし、個人事業主は所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税制度」が適用されるため、収益が大きくなると法人よりも税負担が重くなる可能性があるでしょう。
法人
法人として開業する場合、一般的には「株式会社」を設立します。手続きは個人事業主に比べてやや複雑です。次のような流れで進めます。
- 定款の作成・認証:会社の基本ルールとなる「定款」を作成し、公証役場で認証を受ける。
- 資本金の払込み:代表者(発起人)の口座へ、定款に記載した資本金を入金する。
- 設立登記の申請:法務局で設立登記申請を行う。登記完了日が、会社の設立日となる。
株式会社の設立には、定款認証手数料や登録免許税などで約20万~30万円程度の費用がかかります。しかし、法人化は次のようなメリットがあるため、将来的に事業を拡大したい方に適した形態といえるでしょう。
社会的信用度が高く、金融機関からの融資を受けやすい
個人の資産と会社の資産を明確に分離し、リスク管理ができる
役員報酬を経費として計上できる、赤字を最大10年間繰り越せるなど、税制上の優遇措置が多い
不動産開業と税金の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。
⇒不動産開業で知っておきたい税金|個人事業と法人のメリット・デメリット
6. 不動産開業の流れ ⑤各種手続き
事務所の準備と会社設立が完了したら、次は不動産業を正式に始めるための法的手続きを進めます。
中でも最も重要なのが「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」の取得です。この免許がないと、不動産の売買や賃貸の仲介など、宅建業としての取引を行うことはできません。
申請には複数の要件があるため、事前に確認し、スケジュールを立てて計画的に準備しましょう。
⑤-1.宅地建物取引士の設置
宅建業免許を取得するためには、事務所ごとに「専任の宅地建物取引士(宅建士)」を配置することが法律で定められています。専任とは、原則としてその事務所に常勤し、他の業務と兼任しないことです。
配置人数の目安は、従業員5人につき宅建士1人以上。例えば、従業員が10人の場合、2名以上の宅建士を常駐させる必要があります。
宅建士は、不動産取引における重要事項の説明や契約書(いわゆる「37条書面」)への記名・押印など、独占業務を担う重要な存在です。宅建士がいなければ、適法に仲介業務を行うことはできません。
開業者が宅建士の資格を持っている場合は自身が専任の宅建士になれますが、資格がない場合は有資格者を雇用または専任者として確保しましょう。
宅建士資格取得の流れ
宅建士になるには「試験合格→登録→宅建士証交付」という3ステップを踏みます。試験の日程や内容を確認し、準備を進めましょう。
項目 | 詳細 |
実施公告 | 原則として毎年6月第1金曜日 |
試験案内 | 試験のホームページまたは各都道府県の指定場所で配布 |
受付 | 7月第1営業日から下旬まで |
試験日 | 毎年10月第3日曜日(年1回) |
合格発表 | 11月下旬 |
受験資格 | 年齢・学歴・国籍などの制限なし(誰でも受験可能) |
試験科目 | 権利関係・宅建業法・法令上の制限・税・その他(全50問) |
合格率 | 約15〜17%前後 |
合格ライン | 毎年35点前後(50点満点中) |
試験実施機関 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO) |
宅建士資格の登録
宅建試験に合格しただけでは、まだ宅建士として業務を行えません。宅建士になるためには、試験地の都道府県知事に「宅地建物取引士資格登録」を申請し、登録を完了させる必要があります。
登録時には、登録申請書や身分証明書、住民票、登記されていないことの証明書など複数の書類が必要です。登録まで約1〜2か月ほどかかります。
なお、実務経験が2年以上ない場合は、資格登録の前に「登録実務講習」の受講が必要です。これは、宅建業に関する実務知識や手続きを学ぶための講習で、約2日間で修了できます。修了後は「修了証明書」を発行してもらい、宅建士登録申請時に添付します。
項目 | 詳細 |
対象者 | 不動産業の実務経験が2年未満の合格者 |
期間 | 約2日間(通信+スクーリング形式) |
費用 | 約15,000〜25,000円(講習機関により異なる) |
内容 | 契約書作成、重要事項説明、媒介契約の実務など |
修了後 | 「修了証明書」を登録申請時に添付する |
宅建士証の交付
資格登録が完了したら、次に「宅地建物取引士証(宅建士証)」の交付申請を行います。宅建士証は宅建士として業務を行うための身分証明書であり、これが交付されて初めて重要事項説明などの独占業務に携われるものです。
交付手数料は約5,000円、有効期間は5年間です。更新時には法定講習(1日)を受講する必要があります。宅建士証は取引時に提示する義務があるため、常に携帯してください。
⑤-2.宅地建物取引業の申請
宅建士を配置したら、次は「宅地建物取引業免許」の申請です。これは、不動産会社として営業を行うための免許で、法人・個人のどちらでも申請できます。
免許には、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合の「都道府県知事免許」と、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合の「国土交通大臣免許」の2種類があります。
区分 | 免許区分 | 申請料 |
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合 | 都道府県知事免許 | 3万3,000円 |
複数の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣免許 | 9万円 |
参照:国土交通省「宅地建物取引業の免許について」
開業時は1拠点なら知事免許で始められますが、事務所が複数の都道府県に広がった場合は、大臣免許の取り直しが必要です。免許の申請は、事務所がある都道府県の担当窓口(都市整備課や建築指導課など)で行います。
提出書類は、申請書のほか、商業登記簿謄本、役員の身分証明書、事務所の外観や内部の写真などです。審査期間は1〜2か月程度で、免許の有効期間は5年間になります。継続して営業する場合は、期間満了前に更新手続きが必要です。
⑤-3.保証協会へ加入する
宅建業を始める際は、万が一のトラブルで消費者に損害を与えた場合でも補償できるよう、保証金制度を整えておく必要があります。
本来は、法務局に「営業保証金」を供託する仕組みですが、その金額は本店1,000万円、支店ごとに500万円と高額です。そこで、多くの事業者は、高額な営業保証金を直接供託する代わりに、「宅地建物取引業保証協会」へ加入しています。
この制度を利用すると、法務局への保証金供託の代わりに、以下の費用を保証協会へ納めることで済ませられます。
営業所の種類 | 弁済業務保証金分担金 |
主たる事務所(本店) | 60万円 |
その他の事務所(支店) | 1か所ごとに30万円 |
参照:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会のご案内」
なお、保証協会への加入時には、この分担金に加えて入会金や年会費などの費用も必要です。合計すると、初期費用の目安は130万〜180万円程度となります。費用はかかりますが、高額な営業保証金を準備するのに比べて、開業時の資金負担を大幅に軽減できるでしょう。
7. 不動産開業の流れ ⑥開業
すべての準備と手続きが整ったら、いよいよ正式に不動産会社として営業を開始できます。
しかし、ここからが本当のスタートです。安定した経営基盤を築くためには、効果的な集客戦略(広告・SNS・紹介など)と、業務効率を高める不動産DXの導入が欠かせません。
広告戦略
開業直後は、会社やブランドの知名度がまだ低いため、積極的な集客活動が必要です。現代の不動産ビジネスでは、オンライン集客を中心としたマーケティングが主流となっています。
ポータルサイトへの掲載
大手不動産ポータルサイトに物件情報を掲載するのは、最も基本的な集客手段の一つです。掲載費用はかかりますが、月間数百万人規模のユーザーにリーチでき、短期間で反響を得やすいのが特徴です。
掲載時は、写真の明るさ・キャッチコピー・初期費用や立地の訴求ポイントを明確にし、競合物件との差別化を図りましょう。また、アクセス解析をしてクリック率や問い合わせ率を継続的に改善することで、掲載費用対効果を最大化できます。
自社ホームページ・SNSの活用
集客をポータル任せにせず、自社のWebサイトやSNSで情報発信することも欠かせません。
自社Webサイトでは物件情報に加え、地域の暮らしやお役立ち記事、スタッフ紹介などを掲載することで、信頼性と親近感を高められます。InstagramやTikTokでルームツアー動画、リフォーム事例を投稿すると、若年層にも訴求可能です。
X(旧Twitter)やLINE公式アカウントを活用すれば、フォロワーとの接点を増やし、リピーターや紹介につなげやすくなります。自社メディアを育てることで、長期的に集客資産を構築できるでしょう。
地域密着型のプロモーション
地域密着での集客は、信頼構築と口コミ拡大に直結します。チラシのポスティングや情報誌への掲載、地域イベントへの参加は、地元住民への認知を高める効果的な手段です。
さらに、商店街や自治会との協賛、地域清掃などの社会貢献活動を通じて「顔の見える不動産会社」として信頼を得られます。名刺や配布資料にQRコードを設けてWeb導線を作るのもおすすめです。オフラインとオンラインの相乗効果が生まれ、自然な口コミや紹介を増やせます。
限られた広告予算の中で、どの媒体にどれだけ投資するか、費用対効果を見極めながら戦略を立てることが重要です。
不動産DX
開業したばかりの時期は、一人または少人数で多くの業務をこなさなければなりません。そこで役立つのが、デジタル技術を活用して業務を効率化する「不動産DX」です。DXを取り入れることで、事務作業の負担を減らし、営業や顧客対応に集中できます。
主なDXツールと機能は次のとおりです。
DXツール | 主な機能や内容 |
不動産管理 | 物件/入居者/契約/入出金/保守履歴を一元管理。クラウド型で社内外から安全にアクセス可能。 |
CRM・SFA(顧客管理/営業支援) | 顧客情報・対応履歴・希望条件を一元化し、フォロー漏れ防止と適時提案で成約率向上。 |
電子契約・電子署名 | 印紙・郵送・移動コスト削減、顧客利便性向上。 |
VR・オンライン内見 | VR・オンライン内見 |
例えば「Facilo(ファシロ)」のような不動産仲介に特化したツールを導入すれば、顧客とのやり取りや提案資料作成を自動化できます。少人数でも効率的な営業体制を構築できるでしょう。DXの推進は、単なる業務効率化にとどまらず、顧客満足度の向上や成約率アップを実現する重要な経営戦略です。
開業初期からデジタル化を取り入れると、固定費の削減やサービス品質の向上を両立できます。競合他社と差別化を図れるでしょう。
不動産DXの具体的な手法については、こちらの記事も参考にしてみてください。
⇒不動産業界のDXとは?重要性、導入方法、ツール、成功事例まで解説
8. 不動産開業で失敗しないためのポイント
不動産開業は大きなチャンスがある一方で、準備不足のまま始めてしまうと失敗につながりかねません。
ここでは、失敗のリスクを抑え、早期に事業を軌道に乗せるためのポイントを紹介します。
資金準備を万全にする
不動産開業で最も多い失敗原因の一つが「資金ショート(資金不足)」です。
開業時には、事務所の設置費用や免許申請料、保証協会への加入費、広告・宣伝費など、想像以上に多くの初期費用が発生します。売上が安定するまでの期間を乗り切るためには、少なくとも3〜6か月分の運転資金を確保しておくことが理想です。
自己資金だけでまかなうのが難しい場合は、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や、国・自治体が実施する補助金・助成金制度などを活用しましょう。複数の選択肢を組み合わせることで、資金計画に余裕が生まれ、精神的な安定にもつながります。
差別化とターゲット設定を明確にする
不動産業界は競争が激しく、大手企業と同じやり方で勝負するのは得策ではありません。開業を成功させるためには、自社の強みを活かした「差別化戦略」と、どのような顧客を相手にするかという「ターゲット設定」が重要です。
例えば、次のように特定のニーズに特化することで、競合が少ない分野でトップを目指せます。
単身女性向けのセキュリティ重視物件
学生や新社会人向けの手頃な賃貸物件
外国人対応の物件
ペットと暮らせる賃貸物件
リノベーション向き中古物件
このようにターゲットを明確に設定すると、広告や接客の方針に一貫性が生まれ、より訴求力の高いメッセージを発信できます。結果として、限られた予算でも効果的な集客が可能になり、地域や分野で「選ばれる不動産会社」を目指せるのです。
集客とマーケティングを強化する
どれほど魅力的なサービスを提供していても、顧客に知ってもらえなければ意味がありません。不動産開業後の成功は、いかに効率的に見込み客を集め、成約につなげられるかにかかっています。
集客は、オンラインとオフラインの両面からアプローチしましょう。
オンライン集客では、不動産ポータルサイトへの掲載や自社WebサイトのSEO、SNS運用などを活用して、幅広い層に情報を届けることが可能です。定期的な更新と地域情報の発信により、信頼性と認知度を高められます。
一方、地域での人脈づくりや紹介キャンペーンの実施など、地元密着型のオフライン施策も効果的です。
さらに、集客を成約へとつなげるためには、営業フローの仕組み化が欠かせません。顧客管理ツールを使って顧客情報や対応履歴を一元管理し、継続的にフォローできる体制を整えましょう。少ない人員でも効率的に営業を進められます。
このように、オンラインとオフラインを組み合わせた複数の集客チャネルと、デジタル管理による営業効率化が、長期的に安定した経営を支える鍵となるのです。
9. 不動産開業に関するよくある質問
ここでは、不動産開業に関するよくある質問を紹介します。
Q1.不動産業界未経験でも開業できますか?
Q2.不動産業は1人でできますか?
Q3.不動産起業の成功率はどのくらいですか?
Q4.開業資金は最低いくら必要ですか?
Q5.自宅兼事務所はどこまでOKですか?
Q6.一人で開業する場合、年収はどれくらい見込めますか?
Q1.不動産業界未経験でも開業できますか?
未経験でも開業は可能です。宅建業を行う事務所には専任の宅建士の設置が必須のため、開業者自身が取得するか、有資格者を確保しましょう。
また、実務経験がない分、業界知識や営業ノウハウを補う努力は不可欠です。経験者と共同で開業したり、業務効率化の支援ツールを導入したりするなどの工夫が求められます。
Q2.不動産業は1人でできますか?
はい、宅地建物取引業法では個人事業主としての開業もできます。その際の条件は、専任の宅建士を1名以上配置することです。開業者本人が宅建士の資格を持っている場合、自分を専任宅建士として登録すれば問題なく事業を始められます。
ただし、1人で営業・契約・事務作業まですべて対応しなければならないため、業務を効率化する仕組みづくりが欠かせません。
最近では、不動産DXツールやクラウド型顧客管理システムを導入することで、1人でもスムーズに集客や契約管理ができる環境を整えられます。
Q3.不動産起業の成功率はどのくらいですか?
不動産業者数は一時減少していましたが、平成26年度以降は増加傾向にあります。
直近2年のデータは次のとおりです。
年度 | 宅建業者数 | 新規免許数 | 廃業等件数 |
令和5年度 | 130,463 | 6,242 | 5,268 |
令和6年度 | 132,291 | 6,383 | 4,555 |
参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度末 宅建業者と宅地建物取引士の統計について」
令和6年度における宅建業者数は132,291、廃業等件数は4,555で、年間廃業割合はおよそ3%となっています。
ただし、これは「新規開業した会社の3%が毎年廃業している」という意味ではなく、全登録業者に対する年間の廃業比率です。この数値は他業種と比べて特別に高いわけではなく、不動産業は比較的安定した市場といえるでしょう。
一方で、廃業理由には経営者の高齢化・後継者不足・資金繰りなどが挙げられます。開業前には、十分な資金計画と明確な差別化戦略を立ててください。顧客との信頼関係を丁寧に築いていけば、長く安定した経営を続けられる可能性は十分あります。
Q4.開業資金は最低いくら必要ですか?
開業に必要な資金は、事業形態や事務所の規模によって異なりますが、一般的な目安は約400万〜1,000万円程度です。
主な内訳には、保証協会への加入費(約130万〜180万円)、事務所の契約・内装費、備品購入費、そして数か月分の運転資金などが含まれます。自宅を事務所にするなど、工夫次第で初期費用を抑えられるでしょう。
開業スタイルに合わせて、無理のない資金計画を立てることが大切です。
Q5.自宅兼事務所はどこまでOKですか?
自宅の事務所利用は可能ですが、宅地建物取引業法で定められた事務所の要件を満たす必要があります。
具体的には、居住スペースと事務所スペースを明確に分けること、独立した出入口があること、他の居住部分を通らずにお客様が入室できる構造であることが求められるでしょう。
つまり、生活空間の一角をそのまま使うのではなく「業務専用の空間」として独立していることがポイントです。
Q6.一人で開業する場合、年収はどれくらい見込めますか?
個人で不動産業を営む場合、平均年収はおおよそ600万円前後といわれています。一人で運営するため、売上から経費を差し引いた分がすべて自分の収入となり、努力次第では会社員時代を上回る収入も夢ではありません。
特に高額物件を扱う売買仲介が中心なら、年間数千万円の手数料収入を得るケースもあります。
ただし、案件が少ない時期は収入が不安定になるリスクも否めません。まずは着実に実績を積み重ね、安定した収益基盤を築くことが重要です。
10. 不動産開業は流れを正しく理解して効率的にスタートしよう
不動産の開業には、事業方針の決定・資金準備・事務所設置・免許申請など、いくつもの手順があります。それぞれのステップを正しく理解し、計画的に進めることが、スムーズな開業への近道です。
また、開業後に事業を軌道に乗せるためには、他社との差別化と業務の効率化が欠かせません。特に少人数でスタートする場合は、デジタルツールを活用して、営業・顧客管理・契約業務を効率化しましょう。
不動産コミュニケーションクラウド「Facilo(ファシロ)」は、顧客管理から物件提案、追客の自動化まで、不動産仲介業務に必要な機能が一つになったツールです。煩雑な作業を減らし、少人数でも高い生産性と売上アップをサポートします。
これから不動産開業を目指す方や、業務を効率的に運営したい方は、ぜひFaciloに資料請求やお問い合わせをしてみてください。